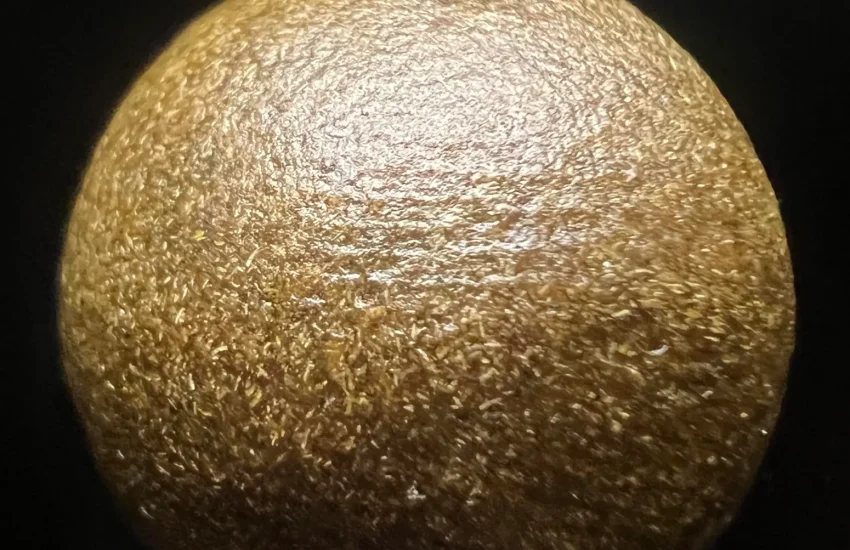ナポレオンは20年間、忠実な部下たちを率いてヨーロッパの軍隊と戦い続けた。圧倒的な不利な状況下での華々しい勝利は、フランス中に誇りと歓喜の渦を巻き起こした。勝利の代償として200万人のフランス人の犠牲が出たとしても、それは問題ではなかった。これらの戦死者は英雄だったのだ。[1]
最終的な敗北と、フランスにもたらした一時的な栄光の恐るべき代償にもかかわらず、ナポレオンは戦場での功績と、特に公民権の分野での国内での功績によって常に記憶されるだろう。
ナポレオンは意図していなかったものの、その軍事的功績によって何千人ものフランス兵がハシシに触れることになりました。この儀式は1798年のフランスによるエジプト侵攻の結果として行われ、ナポレオンは兵士たちが麻薬に耽溺することで、放縦で無秩序な行動をとるようになるのではないかと懸念しました。
当時も今も、軍隊生活は基本的に終わりのないルーチンと乗り越えられないほどの退屈の連続でした。時間をつぶすために、意識を失うまで酒に溺れる兵士もいました。しかし、イスラム教支配下のエジプトでは、アルコールは好んで使われる酔わせるものではありません。エジプト人は別の薬物を好み、その薬物とは当然ハシシでした。ハシシの習慣は兵士たちの間で広く蔓延したため、1800年10月、ナポレオンはフランス占領軍に対し、次のような布告を出しました。
エジプト全土において、ハシシを原料とした特定のイスラム教飲料の摂取、およびハシシの種子から発生する煙の吸入は禁じられています。この植物を習慣的に飲んだり吸ったりする者は理性を失い、あらゆる過度の行為に身を委ねる者の運命である激しいせん妄に陥ります。[2]
兵士たちは命令を聞き、おそらく同意の意を表して頷き、すぐにハシシを使い始めた。兵士たちに加え、ナポレオンが国と国民の調査のために連れてきた3人のフランス人科学者――シルヴェストル・ド・サシー、ルイエ、デジュネット――もハシシを使い始めた。表向きは、この薬物が人体にどのような影響を与えるかを自ら確かめるためだった。ハシシの経験に興味をそそられた彼らは、同僚たちが研究室でさらに実験を行うため、ハシシをフランスに送り返した。
最初の研究は1803年に出版されたヴィリー博士によるもので、彼はハシシの様々な抽出物を作製し、その謎めいた有効成分の解明を目指しました。ヴィリー博士は、この薬物を徹底的に研究した結果、ハシシはトロイのヘレネーが客人を麻痺させて昏睡状態に陥らせるために使用した謎のウツボカズラに他ならないと結論づけました。
軍が帰還して間もなく、フランスではハシシの驚くべき効能について、実際にハシシを使用した兵士たちや、エジプトで軍務に就き、この薬物とその神秘性を研究する機会を得たフランスの科学者たちから聞かされるようになりました。例えば、軍がフランスに帰還して間もなく、当時世界有数のアラビア学者であったシルヴェストル・ド・サシーは、十字軍時代に中東を恐怖に陥れたアラブの暗殺集団「アサシン」の名称の由来という長年の謎をついに解明したと発表しました。1809年のフランス学士院での演説で、シルヴェストル・ド・サシーは「アサシン」という言葉は、アラブ世界で草やハーブを意味する一般的な用語であるハシシに由来していると主張しました。そして、大麻は草のようなものと考えられており、マルコ・ポーロが言及した謎の薬は実際にはハシシであると主張しました。
ハシシによって引き起こされる酩酊状態は一時的な狂気状態に陥らせ、衰弱していることに全く気づかないうちに、使用者は公共の平和を乱すような残虐な行為に及ぶことがある…麻、あるいはその植物の一部が、我々には知られていない他の物質と混ぜられ、狂乱と暴力の状態を作り出すために時々使われてきた可能性は否定できない。[3]
1818年、ウィーンの作家ヨーゼフ・フォン・ハンマー=プルクシュタルは、ヨーロッパにおけるアサシン教団と、アラブ世界の異国情緒あふれる麻薬であるハシシに関する物語への関心の高さを利用し、この宗派に関する初の長編小説を出版しました。当初はドイツ語で出版されましたが、非常に人気を博し、すぐにフランス語(1833年)と英語(1835年)に翻訳されました。ハシシとアサシン教団の結びつきは、この時代から大麻の民間伝承に深く刻み込まれていきました。
ドラッグと夢
1800年以前、フランスの文学、旅行書、植物学書のすべてにおいて、大麻に関する言及はわずか10件程度でした。1800年から1850年の間に、フランスでは大麻に関する記事や書籍が30冊以上出版されました。ハシシ酩酊状態、薬物誘発性幻覚、そして「二重意識」といった物語を描いた『千夜一夜物語』は、長年にわたりベストセラーリストのトップを飾りました。著名な東洋学者シルヴェストル・ド・サシーは、ハシシがエクスタシー、せん妄、狂気、そして死さえも引き起こすと警告し、人々の大麻への関心をさらに掻き立てました。
この奇妙な薬物をめぐる騒動に魅了された人々のなかには、大麻が精神に及ぼす特異な効果が創造性を高める手段になるかもしれないと考えた若い作家、詩人、芸術家が数多くいた。
ナポレオン戦争後のフランス、そしてヨーロッパ全体は、魂の探求の時代でした。人々は、戦争をより恐ろしいものにしただけの「理性的な時代」の成果に幻滅し、人間の心の奥深くに埋もれ、夢の中でしか垣間見ることのできない、隠された非理性的で感情的な自己を求めていたようです。もしこの隠された世界への入り口を見つけることができれば、無意識と交信できるかもしれません。
当初、彼らはアヘンに頼っていました。アヘンの精神的な啓発力の可能性は、 1821年にロンドン・マガジンに掲載された一連の記事によって文壇の注目を集めました。これらの「アヘン中毒者の告白」の著者であるトーマス・ド・クインシーは、この精神を変容させる薬物の世界に毎週足を踏み入れ、後に中毒の結果として苦しむことになる耐え難い苦痛を描写することで、読者を魅了しました。多くの作家にとって、アヘンは、彼らを意識の現実世界に縛り付ける目に見えない束縛を解く鍵となることを約束していました。一度解放されれば、隠された創造のミューズを呼び起こすことができるかもしれません。薬物に触発された夢と変性意識から、物語のプロット、詩のイメージ、芸術のアイデアが生まれるかもしれません。
小説家、詩人、芸術家たちが最初にアヘンに惹かれたのは、特に夢を誘発する可能性があることでした。多くの文豪たちは夢の記録を取り、それを作品に活かしました。ブラウニング、コールリッジ、ポー、ワーズワースなどは皆、ベッドサイドにメモ帳とペンを置き、毎晩夢のミューズが訪れる様子を記録していました。夢を思い出せないことは、作家の創造性にとって残念な損失でした。麻薬によって誘発された夢は、一口飲むごとに創造性を高めることを約束していました。
しかし、これまで到達不可能だった人間の精神の領域へとこの道を選んだ多くの人々は、後にその決断を後悔した。中毒の苦しみを味わったのはド・クインシーだけではなかった。麻薬地獄での経験は、アヘンの望ましい効果を持ちながらも、その悪夢のような性質を持たない、別の薬物、別の種類の化学合成物を求めるきっかけとなった。
そのような薬物に関する噂は数多くありました。エジプト戦役の退役軍人たちは、アラビアンナイトから抜け出してきたかのような薬物、ハシシについてよく語っていました。また、パリの著名な医師がこの薬物の試験のためにボランティアを募集しているという噂もありました。
ハシシと狂気
ジャック=ジョゼフ・モロー博士(1804-1884)は、精神医学の最も重要な革新者の一人であるジャン・エスキロールに師事しました。例えば、精神科医たちが、精神衰弱に先立つ出来事が精神疾患の謎を解く鍵となる場合があることに気づき始めたのは、エスキロールの影響によるものでした。また、モローのような精神科医たちが幻覚に興味を持つようになったのも、エスキロールの影響によるものでした。彼らは、精神医学が幻覚の原因を特定できれば、精神異常そのものの原因にも迫れる可能性があると考えました。
因果関係と幻覚が精神疾患を理解し治療する鍵であると教師が強調したことに深く感銘を受けたモローは、精神衰弱に陥ることなく狂気を経験する方法について考えました。
普通のうつ病を理解するには、それを経験する必要があります。狂人の狂言を理解するには、自分自身が狂ったことを経験したことが必要ですが、自分の狂気の認識を失わず、心に起こる精神的変化を評価する力を失ってはなりません。[4]
患者がどのような症状を経験しているかを知ることで、モローは最終的に精神病状態を理解し、治療法を考案できると考えました。この「模型精神病」を作り出すために彼が用いたのはハシシでした。
モローが初めてハシシを試したのは、1830年代のアラブ諸国旅行中だった。彼は他の医師の著作を通してハシシの効能の一部について既に知っていたことは間違いないが、1840年にオーバール・ロッシュ博士の「東洋におけるチフスと疫病について」という科学論文を読んで初めて、ハシシが精神を探求する可能性に興味を持つようになった。ロッシュは、エジプト人がハシシを愛用していたため、ヨーロッパ人を苦しめた病気にかかりにくかったと主張しただけだったが、モローはこの薬物の他の用途について真剣に考えるようになった。
「人間には二つの存在様式、二つの生の様式が与えられている」とモローは思索した。「一つ目は外界、宇宙との交わりから生じる。二つ目は自己の反映に過ぎず、それ自身の明確な内的源泉から養われる。夢とは、外的生が終わり、内的生が始まる中間の地である。」[5] 彼は、ハシシの助けを借りれば、誰もがこの中間の地へ自由に入ることができると感じていた。
ハシシの研究を進める中で、モローは摂取量と効果の間に奇妙な関係があることに気づき始めた。少量では、多幸感、静寂、倦怠感、そして無関心といった感覚が生じた。摂取量を増やすと、注意力が散漫になり、考えがランダムに浮かぶようになった。時間の感覚が歪み、分が数時間に感じられた。思考が次々と交錯し、感覚が鋭敏になったように感じられた。さらに摂取量を増やすと、夢が脳に押し寄せ始めた。モローが見た夢は、まるで狂気の幻覚のようだった。
モローはハシシを用いた実験を通して、当時の多くの著名な精神科医が主張したように、精神異常は脳損傷によるものではなく、脳機能の変化、つまり神経系における化学的変化によって引き起こされるものであるという結論に至った。100年後、LSDを研究していた精神科医たちも同様の結論に至った。
ハシシの供給が限られていたため、モローはハシシの治療への応用の可能性を探ることはやめました。その代わりに、ハシシ体験を精神病のモデルとして用いるという当初の考えを貫くことにしました。しかし、こうした研究を行うには、ハシシの効果を客観的に観察できなければなりませんでした。彼は自分自身で実験を行うことで、この薬物が精神に及ぼす影響についてある程度の洞察を得ていました。しかし、こうした主観的な印象は不正確ではないでしょうか。ハシシは時間の感覚を歪めます。他の印象も歪めるのではないでしょうか。ボランティアの協力を得ることによってのみ、彼はハシシの幻覚から解放された状態で、他者に対する薬物の効果を観察することができました。冷静な科学者としてのこの役割において、モローはフランスの著名な作家、詩人、芸術家で構成されるハシシ・クラブで薬物を配給するようになりました。
モローの精神薬理学における研究は、薬物が脳に及ぼす影響を研究する先駆的なアプローチとして現在では認められているが、彼の同僚たちは彼の研究の価値と重要性を認識していなかった。
1846年、439ページに及ぶ著書『ハシシと精神病 心理学的研究』を出版した翌年、モローはフランス科学アカデミー主催のコンテストにその著書を応募することを決意した。他の応募作には、医学、外科、神経学に関する他の著書も含まれていた。応募作のうち6冊が賞を受賞し、2冊が佳作に選ばれ、その中にモローの著書もあった。薬剤の投与量と主観的効果の興味深い関係に審査員の1人が感銘を受けていなかったら、この栄誉さえも逃していたかもしれない。モローはハシシを研究し、精神異常の研究手段として薬剤を提案した最も初期の科学者の1人であったが、テオフィル・ゴーティエとハシシ・クラブがなかったら、おそらくモローは今以上に無名になっていただろう。
しかし、フランスの科学者たちはハシシに無関心だったどころか、その治療効果に強い好奇心と興味を抱いていたようだ。1847年、パリ薬学協会は大麻の有効成分の単離に対して賞を授与し、最終的に1857年に受賞した。1848年には、ハシシに関する最初の博士論文がドゥクールティーヴによって執筆された。後にシャルル・ボードレールは、ハシシに関する多くの情報源としてドゥクールティーヴの薬局方を頼りにした。
ハシシの先駆者
フランス世界でハシシに意識拡張の鍵を求めた著名人の中に、ピエール・ジュール・テオフィル・ゴーティエがいました。画家としても詩人としても失敗したゴーティエは、1835年、24歳にして女装家の物語『マダム・ド・モーパン』を発表し、一夜にして一世を風靡しました。ある批評家はこの作品を「本格的なロマン主義作家が書き上げた小説の中で最も大胆な作品」と称賛しました。[6]
ゴーティエの人生観は、この小説の序文に最もよく表れている。彼は読者にこう語りかける。「新たな喜びを発明する人々には特別な賞が与えられるべきだ。なぜなら、私にとって喜びこそが人生の目的であり、この世で唯一有用なもののように思えるからだ。」[7]
もしゴーティエが望む通りに事が運べたなら、この賞の最初の受賞者の一人は、彼にハシシの素晴らしさを教えてくれたモローだったに違いありません。モローとの出会いをきっかけに、ゴーティエは後に有名なハシシ・クラブ(クラブ・デ・ハチシャン)を設立し、パリのカルチエ・ラタンにある優美なホテル・ローザンで毎月会合を開いていました。この会合でモローは、アレクサンドル・デュマ、ジェラール・ド・ネルヴァル、ヴィクトル・ユーゴー、フェルディナン・ボワサール、ウジェーヌ・ドラクロワ、そしてゴーティエ自身といった著名人に、ダワメスク(ハシシ、シナモン、クローブ、ナツメグ、ピスタチオ、砂糖、オレンジジュース、バター、カンタリドの混合物)を振る舞っていました。
ゴーティエ自身のハシシへの興味は、主に好奇心から生まれたものでした。エジプトで初めてこの薬物を試したフランス兵の噂話を聞き、興味をそそられたのです。ゴーティエはまた、フランス国民も自分と同じようにハシシに興味を持つだろうと洞察するほどの洞察力を持っていました。彼らもこの謎めいた薬物に関する話を耳にしており、『千夜一夜物語』をはじめとするアラブ諸国を題材にした書籍の人気は、この種の記事が売れることを証明していました。
1843年、フランソワ・ラルマンは匿名で『ハシシ』を出版した。これはハシシをプロットの仕掛けとして初めて用いた作品である。この本は人気を博し、1848年に再版され、今度はラルマンの名が著者となった。しかし、人々の想像力を捉え、揺るぎないものにしたのは、同じく1843年に出版されたゴーティエの『ハシシ』であった。これは比較的短い作品で、ゴーティエがハシシの影響下で経験した様々な幻覚――色彩や模様の変化、体の変形、そして色を聞き音を見る感覚(共感覚として知られる現象)――を描写しており、その人気はゴーティエにさらなる執筆を促すことになった。
彼の2番目の論文は1846年に『ルヴュ・デ・ドゥ・モンド』に掲載され、「ハシシのクラブ」と題された。ハシシの影響下での体験については、彼が既に記述していた内容とほとんど同じ内容だったが、ホテル・ローザンとそこに集まるクラブのメンバーについての記述により、このテーマに関する彼の著作の中でも最もよく知られるものとなった。
ゴーティエによって不朽の名声を得たこのホテルは、1657年にローザン公爵によって私邸として建てられ、公爵は1723年に90歳で亡くなるまでそこに住んでいました。当時は壮大な建築的偉業でしたが、1840年代には見るべきものというよりはむしろ荒廃していました。建設当時は3階建てで、パリの高層ビルの一つでした。大きな窓、小さなガラス板、そして石造りのバルコニーは街のランドマークでした。正面玄関の左側には、赤、明るい黄色、そして金色の鉄の柱が立っていました。2階の高さには、公爵を訪ねるすべての人々を見下ろすガーゴイルのドラゴンがいました。ゴーティエのハシシに関する著作の人気は、ハシシ体験の描写というよりも、ハシシ・クラブの集会場と、そこに集まって麻薬を摂取する著名人たちの陰鬱な雰囲気によるものだと言われています。
ゴーティエの記事は、たちまち読者を魅了した。ゴーティエは綿密に雰囲気を醸し出す。夜。セーヌ川には霧が漂い、何も見分けがつかない。形はぼんやりと、かすかに見え隠れする。ようやくホテルを見つけ、ノックすると、年老いたポーターが「細い指を外側に伸ばして」道を指し示した。
階段の頂上で彼を迎える人々の中に、謎めいた医師(モロー)がおり、彼は彼に「水晶の花瓶から親指ほどの大きさの緑がかったジャムのペーストの一片」を手渡し、「これは天国でのあなたの分け前から差し引かれます」と警告した。[8]
ゴーティエはその後、読者に山の老人と暗殺者について語り続け、「医者が我々に配ったばかりの緑色のペーストは、まさに山の老人が狂信者たちに投与していたものである…つまりハシシであり、そこからハシシーン、あるいはハシシを食べる人、つまり「暗殺者」という言葉の語源が生まれ、その凶暴な意味は山の老人の信者たちの血に飢えた習慣から容易に説明できる」と述べている。[9]
ハシシと死の不吉な関係は、ゴーティエが食卓に並んだ客たちの描写の中でさらに展開される。「長髪、あごひげ、口ひげ、あるいは髪の毛を少し剃った客たちが、16世紀の短剣やマレーの民族衣装、ナバハスを振り回している…」[10]
食事が終わりに近づくにつれ、ゴーティエは幻覚を見始める。食卓の人々の顔の形と色が変わり、「岩に泡立つ波が再び押し寄せるように、狂気が私の脳に入り込み、そして去っていき、ついには完全に脳を侵食した」[11]。
客たちは応接室へと退散する。ゴーティエは暖炉の傍らの椅子に深く腰掛け、麻薬に身を委ねる。考えに耽る彼は、部屋に他の人がいることは分かっているものの、誰も見当たらない。彼は完全に自分の世界に浸りきっており、心の中には顔も体も怪物のように歪んだグロテスクな人物たちが浮かんでいた。
物語の残りの部分にも、同様の要素が数多く含まれている。ゴーティエが思い起こさせるイメージは、ホテル・ローザンのゴシック様式の内装に完璧に溶け込んでいる。幻覚に耽る彼の思考を縫うように走るグロテスクな影は、周囲の環境に大きく影響を受けている。ゴーティエの描写から、読者はハシシこそが、まさに想像力のステュクス川を渡って狂気の冥界へと乗客を運ぶ船頭であることを感じ取る。
ハシシの吟遊詩人
クラブ・デ・ハチチンで最も有名なメンバーは、間違いなく陰鬱でメランコリックなシャルル・ボードレールでしょう。ボードレールはドラッグと無縁ではありませんでした。若い頃、彼はラテン・クォーターに住んでいました。そこはパリの1960年代のサンフランシスコのヘイト・アシュベリー地区のような場所で、主に学生、作家、芸術家、そして泥棒が住んでいました。通りは狭く、薄暗く、悪臭が漂っていました。学生たちはカフェやレストランに「たむろ」し、酒盛りをし、現実の、あるいは想像上の性的征服について自慢していました。彼らは酒を飲み過ぎ、アヘンやハシシといった最新の悪徳に耽っていました。
ボードレールは1849年半ば、共通の友人である画家フェルナン・ボワサールを通じてゴーティエと初めて出会いました。ボワサールとゴーティエは共にホテル・ローザンの住人で、その過程でボードレールはハシシ・クラブの会合に招待されました。しかし、常に孤独なボードレールは、この招待をほとんど受け入れませんでした。
1868年に出版された『悪の華』 (Fleurs du Mal)の序文で、ボードレールはこうした秘密の夜会には普段は参加せず、参加したとしても傍観者としてのみだったと告白している。ゴーティエもこの告白を裏付けている。
ボードレールが生理学的な実験として一度か二度ハシシを試したことはあり得るし、おそらくあっただろう。しかし、彼はそれを継続的に摂取することはなかった。さらに、薬局で買ってベストのポケットに忍ばせるような幸福感に強い嫌悪感を抱いており、それがもたらす恍惚感を、本物の家具や本物の花の香りが漂う庭園ではなく、キャンバスに描かれた絵や荒削りな風景画に取って代わられる狂人の恍惚感に例えていた。彼は、私たちのクラブが集まっていたピモダン・ハウス(ホテル・ローザン)での会合には、めったに来ず、ただ傍観者として参加しただけだった…[12]
ゴーティエ自身は「10回ほど試した後、ハシシをやめた。身体に悪影響があったからではなく、真の作家は自身の自然な夢以外何も必要とせず、いかなる機関の影響によっても自分の思考をコントロールされることを気にしないからだ」と語った。[13]
ボードレールは、ハシシに関する最も有名な著作『人工楽園』の序文で、この薬物の作用に関する情報の多くは、長年ハシシを使用している友人との会話で蓄積した詳細なメモに頼っていたことを率直に認めている。他の2つの主要な情報源は、シルヴェストル・ド・サシーの著作と、当時人気のあった薬学書である『実用薬学の実験室あるいは総合百科事典』で、ボードレールはその一部を逐語的に書き写した。後者は1844年に薬剤師ドルヴォーによって初めて出版され、薬物に関する標準的な参考書となった(1847年、1850年、1855年に再版・増補された)。ボードレールは、1858年に出版した『人工楽園』に、ドルヴォーの1850年版のハシシに関する資料の約4分の3を組み込んだが、ボードレールの著作のどこにもドルヴォーについて言及されていない。
『人工楽園』は二部に分かれている。第一部にはボードレールの「ハシシの詩」が、第二部にはド・クインシーの『阿片常用者の告白』の翻訳が収録されている。ボードレールがこの二作品を一冊にまとめたのは、両薬物が非常に似た作用をもたらすと感じていたためである。実際、「阿片の詩」の様々な箇所では、ボードレールが阿片について書いているのか、それとも阿片について書いているのかを見分けるのが困難な場合もある。
ボードレールは、ハシシの最も明晰で分析的な愛好者であると同時に、最も悲劇的な犠牲者の一人としても広く称賛されているが、ハシシの愛好者でも被害者でもなかった。彼は単にハシシの効能を観察したに過ぎず、ハシシの過剰摂取ではなく梅毒で亡くなった。しかしながら、エッセイの最後に表明された痛烈な非難はさておき、ボードレールの『人工楽園』は、文学においてハシシ体験を最も詩的に描写した作品として他に類を見ない。ゴーティエは後にこの本について次のように記している。
医学的に言えば、『人工楽園』はハシシに関する非常によく書かれた論文であり、科学はそこから信頼できる情報を見出すかもしれない。ボードレールは綿密な正確さにこだわり、ハシシに自然と適応した主題にほんのわずかな詩的なイメージさえも持ち込むことは決してなかったからである。[14]
ボードレールは、ハシシが人を全く別の人間に変えてしまうという説を反駁することから議論を始める。「ハシシには奇跡的なものは何もなく、あくまでも自然の誇張に過ぎない」と彼は言う。「ハシシが作用する脳と生体は、その個人に特有の正常な現象のみを生み出す。確かに、その数と力は増大するが、常に本来の姿に忠実である。」[15]
次に彼は、使用者がハシシを摂取する際には適切な心構えを持つようにと警告する。ハシシは個人の自然な行動を誇張するのと同様に、使用者の直接的な感情を強めるからである。注意を要する義務は、使用者が本来快いはずの薬物効果を楽しむことを妨げ、むしろ不安に苛まれ、耐え難い苦痛に苛まれることになる。
適切な準備が整うと、ハシシ使用者は3つの段階を連続して経験します。最初の段階は比較的ゆっくりと、ほとんど気づかないうちに始まります。初心者はハシシの効果について事前に何らかの説明を受けている可能性が高いため、ボードレールは読者に対し、焦燥感を覚える可能性が高いと助言しています。ボードレールは、この焦燥感は初心者を不安状態に陥れる可能性があるため、克服しなければならないと警告しています。使用者が何を言おうと、麻薬が効き始めている兆候は、抑えきれない笑いです。些細な発言にも新たな意味が生まれます。違和感、言葉遊び、滑稽な状況といった感覚は、ハシシの陽気さの特徴です。ハシシが効き始めている2つ目の兆候は、思考回路を維持できなくなることです。思考が頭の中を駆け巡り、支離滅裂になり、断片化し、孤立していきます。もはや会話は不可能です。
酩酊状態の第二段階は、四肢の冷感と全身の倦怠感を特徴とする。昏睡状態と麻痺状態になる。口の中は信じられないほどの渇きでカラカラになる。感覚が研ぎ澄まされ、想像上のものが浮かび上がる。感覚が混乱し、音に色彩が加わり、色彩の中に音楽が宿る。この段階になると、実際には存在しないものが見え、聞こえ始める。
最終段階は静寂に包まれます。時間と空間は意味を失い、物質を超越したような感覚が生まれます。この状態で、究極の思考が意識に浮かび上がります。「私は神になった。」
ボードレールはハシシの酩酊の段階を辿った後、「道徳」と題された章でエッセイを締めくくっています。ここでボードレールはハシシの後遺症について論じています。ハシシには危険な身体的影響はないと述べていますが、使用者の精神的健康については同じことが言えないと主張しています。ハシシは創造性と想像力を高めるものの、インスピレーションを得るためにこの薬物に頼るようになった人は、その虜になり、ハシシを服用しない限り、全く創造的に考えることができなくなる可能性があります。さらに、ハシシは意志力を弱めるため、使用者はこの薬物から得られる創造的な洞察から利益を得ることができなくなります。ハシシによって天地のあらゆる快楽を瞬時に実現できるのであれば、なぜそのような目標を積極的に追求する必要があるのか、と彼は問いかけます。
ボードレールは自殺未遂の直後、ホテル・ローザンから出て行った。梅毒を患い、大酒を飲み、根深い絶望感と自己嫌悪に対処するために阿片に頼り続けていた。作家仲間や批評家からは尊敬されていたものの、ボードレールは自らを失敗者だと考えていた。1866年、若い頃に感染した梅毒菌によって脳が衰弱し、死去した。
バルザックとフローベール
ボードレールは、ハシシ・クラブの会合に出席しなかったことで有名な人物の一人ではなかった。ボードレールが指摘するように、オノレ・ド・バルザックもまた、モローが配る「緑のペースト」を自ら摂取することなく、議事進行を傍聴することを好んだ。
バルザックは、人間にとって自らの意志を放棄することほど深い恥辱や苦しみはないと信じていたに違いない。私はかつて、ハシシの驚異的な効能について議論されていた会合で彼を見かけたことがある。彼は面白おかしくも活発な様子で耳を傾け、質問を続けた。彼を知る者なら、彼が興味を持っていたことは容易に想像できるだろう。しかし、自分の意志に反して考えるという考えは、彼に深い衝撃を与えた。ダワメスクを勧められた彼は、それをじっくりと吟味し、匂いを嗅ぎ、そして触れることなく返した。子供じみた好奇心と、放棄することへの嫌悪感との間の葛藤が、彼の表情豊かな顔に鮮やかに表れていた。自己尊厳への愛が勝利したのだ。[16]
ゴーティエ氏はそのときのことを次のように回想している。
私はその夜ピモダン・ハウスにいたので、この話の絶対的な正確さを保証できる立場にあります。ただ一つ、特徴的な点を付け加えておきます。バルザックは、差し出されたスプーン一杯のダワメスクを返しながら、「テストを受けても無駄だ。ハシシは自分の脳に何の効果もないと確信しているからだ」と言ったのです。[17]
しかし、バルザックの好奇心はついに彼を圧倒し、1845年12月23日付のマダム・ハンスカ宛の手紙の中で、彼はハシシ・クラブの集まりでついにハシシを摂取したことを告白し、グループを離れる際に天上の声が聞こえ、神々しい絵画が見え始めたと付け加えている。[18]
ボードレールのハシシ体験の描写に深く影響を受け、バルザックと同様に自らハシシを試すことにある種の不安を抱いたフランスの著名な作家の一人、ギュスターヴ・フローベールがいた。ボードレールはフローベールに『人工楽園』の私物を贈り、その返信の手紙の中でフローベールは「これらの薬物は常に私の中に強い憧れを掻き立ててきました。化学者のガスティネルに素晴らしいハシシを作ってもらいました。しかし、それは私を怖がらせます!私はひどく自分を責めています!」と告白している。[19]
フロベールはハシシを摂取するかもしれないという不安を抱えながらも、ボードレールがハシシを邪悪なものとして描写していることに異議を唱えた。フロベールにとって、ボードレールのハシシ非難は、本来であれば素晴らしいエッセイだったこのエッセイを台無しにしてしまった。「私には、これほどまでに卓越した主題、科学の始まりともいえるこの著作、自然観察と帰納法の産物において、あなたは悪の精神を強調しすぎているように思われます。ハシシとアヘンの過剰使用を非難するのは避けてほしかった。邪悪なのは薬物そのものではなく、むしろこれらの物質の誤用なのです。」[20]
フローベールは死の直前、ボードレールによるハシシの効能の記述を基に、 『螺旋』と題する自身の小説のアウトラインを書き始めていた。フローベールの手記には、苦悩する主人公が最終的に精神病院に収容される様子が描かれている。彼の精神崩壊の原因は、アラブ諸国への旅行中に身につけた麻薬中毒、ハシシと、この麻薬が作用した並外れた想像力と空想癖だった。ハシシで満たされた彼の脳は、恍惚とした幻覚を作り出し、「永続的な夢遊病」状態に陥り、痛みを感じなくなった。
ハシシの悲劇の使徒
ジェラール・ド・ネルヴァルもまた著名なフランス人作家で、ハシシ・クラブに所属し、著書の中でこの薬物について書いています。ボードレールと同様に、ネルヴァルも憂鬱に悩まされていました。人生の大半を貧困と放蕩の中で過ごしました。また、ボードレールと同様に、ネルヴァルも自殺を図りました。しかし、ボードレールとは異なり、ネルヴァルは自殺に成功しました。
ネルヴァルはパリの学生時代にテオフィル・ゴーティエと出会い、二人は生涯の友となった。ゴーティエを通じて、ネルヴァルはクラブ・デ・ハチシャンの会員となった。
ネルヴァルの最初の大きな文学的成功は、彼がまだ20歳の時に出版された『ファウスト』の翻訳でした。悪魔に魂を売った男の物語は彼の神秘的な関心に訴えかけ、彼の心を神秘的で超越的な道へと導いた数多くの物語の一つに過ぎませんでした。『東洋航海記』(1847年)に記されている近東への旅の途中で、ネルヴァルは「カリフ・ハーケン物語」の着想を得ました。これは、ハシシと二重意識を描いた、他に類を見ないエキゾチックな物語です。
物語の主人公は二重の存在である。昼間はエジプトの支配者であるカリフであり、夜は奴隷の服を着て民衆の間をさまよう。物語の冒頭、カリフはオケルと呼ばれる「(酩酊に対する)禁令を無視して、異教徒たちがワイン、ブーザ(ビール)、あるいはハシシで酔っ払うためにやって来る家の一つ」に入る。彼は「緑がかったペースト」の形で運ばれてきたハシシを注文し、出会ったばかりの仲間とそれを味わう。麻薬が運ばれてくると、もう一人の男が「この箱には、預言者ムハンマドが信者たちに約束した楽園が入っています…」と言う。
ネルヴァルはカリフが経験する様々な感情を描写している。抑えきれない笑い、倦怠感、思考の渦、幻覚、そして完全なリラックス感。この特異な体験の最中、カリフは自分が神であると宣言する。この発言は他の客を冒涜行為として非難させ、カリフは激しく殴打される。彼はまだハシシ体験を習得していなかったため許されるものの、この考えは彼の心に焼き付き、精神病院に送られる。入院中、有名なアラブ人医師アヴィセンナが彼を訪ねる。アヴィセンナはカリフの抗議と、自分がカリフであると主張する主張を、ハシシに狂った狂人の戯言として退ける。
物語のクライマックスは、カリフが精神病院から脱出し、玉座に座る別の人物を目撃する場面です。その人物は自身と酷似しており、ドッペルゲンガーに違いありません。これは、カリフがこれまで知らなかった存在のもう一つの側面でした。最終的に、奇妙な状況が重なり、カリフは肉体的に殺害されますが、玉座に座る彼の霊的存在はエジプトを統治し続けます。
ネルヴァルの寓話の要点は、ハシシの陰険な影響下では、現実と幻想を切り離すことができなくなるという点にある。ハシシ使用者は呪縛にかかっており、ある観念が他のすべてを拒絶するほど心に刻み込まれ、この観念が様々なレベルで自己認識を決定づける。ハシシ使用者は肉体と精神の両方の実体を帯びる。心と体は分離するが、その間ずっと魂は意識的に、そして冷静に、それぞれに起こることを観察する。
ネルヴァルもまた、アヘンを重要な役割とする物語をいくつか執筆した。ボードレールと同様、彼も薬物乱用を経験した。晩年は貧困と悲惨の中で過ごした。数々の悲劇的な恋愛によって、既に薄れかけていた正気はますます悪化し、もはや耐えられなくなったネルヴァルは首を吊った。
アレクサンドル・デュマ
ハシシを題材にした著作を持つハチシャンクラブの4人目の著名なメンバーは、アレクサンドル・デュマです。彼は19世紀半ばのフランス作家の中でも、最も多作でエンターテイメント性に富んだ作家の一人です。ホテル・ローザンの集まりに出席することでハシシの効能をよく理解していましたが、デュマがハシシやその他の薬物を過剰に使用したという証拠はありません。ゴーティエと同様に、デュマはハシシがフランスの読者を魅了する神秘的な魅力を持っていることを鋭く見抜き、彼の代表作の一つである『モンテ・クリスト伯』では、ハシシをプロットの一部にすることで、読者の関心を高めました。『モンテ・クリスト伯』の「船乗りシンドバッド」という章で、デュマはフランツが無人島に住み、自らをシンドバッドと呼ぶ謎めいた見知らぬ男と出会う様子を描いています。
フランツは、密輸の拠点として使われることもあるこの島に、狩りをするためにやって来ました。密輸業者たちに出会い、彼らのリーダーであるシンドバッドに食事に招かれます。シンドバッドの住まいは島の地下にあります。部外者に住まいの入り口を知られないよう、シンドバッドはフランツの目隠しをし、世界中の品々で豪華に飾られた地下宮殿へと案内します。
豪華な食事の後、召使いがテーブルにカップを置く。フランツはカップの蓋を開けると、「緑がかったペースト」が見える。「これを味わってみてください」と召使いはペーストを差し出し、「可能性の境界は消え、無限の空間が目の前に広がり、心も精神も自由になり、束縛されない夢想の果てしない世界へと踏み出すのです」と言う。
シンドバッドは自らペーストを少し取り、休憩中にフランツにアサシンの物語を語る。すると、緑色のペーストの謎がフランツに明らかになる。「これはハシシだ!」とフランツは叫ぶ。
好奇心が高まったフランツも薬を飲み、二人は贅沢に家具が備え付けられた別の部屋に行き、そこでくつろぎながらアラブ世界の大都市を訪れた話などをした。
フランツはハシシの様々な効果を体験し、ついに眠りに落ちた。目が覚めると、彼は地上にいて、一人ぼっちだった。宮殿へ戻るために入り口を探そうとするが、あまりにも巧妙に隠されていた。フランツはこの冒険に疑問を抱き始めるが、待っていた召使いが遠くに浮かぶ船を指差す。望遠鏡で船を覗くと、フランツは船の甲板に一人で立つシンドバッドの姿を見分けることができた。それは夢ではなかった。現実の出来事だったのだ。
フランツと謎めいた主人との出会い、地下宮殿、目隠し、ハシシの手ほどき、彼が体験した幻覚、そして夢のような印象は、読者の興味を惹きつけるように巧みに描かれている。これらはデュマの語り手としての卓越した才能を示す好例である。そして同時に、デュマの繊細で卓越した技巧を示す好例でもある。読者が実際に目にしたのは、マルコ・ポーロの「山の老人と暗殺団」の物語の、まさにその解釈なのだ。
謎めいたシンドバッドはハサンに他ならない。洞窟はアラモートの要塞。密輸業者はアサシン。壮麗な宮殿は伝説の楽園。フランツは目隠しをされ、志願者(フィダイ)たちは地上に入る前に意識を失う薬を与えられ、フランツと同様に意識を失った状態で地上から連れ出される。この比喩は非常に巧妙で、マルコ・ポーロの物語を知っている読者でさえ、モンテ・クリスト物語でまさに同じ伝説に出会っていることに気づかないほどである。
イギリスのハシシ
フランスの著名な文学者によるハシシ体験のセンセーショナルな記述は海峡の向こう側でも注目されず、間もなくイギリスの作家や学生もこの薬物を実験するようになった。
1845年、トーマス・ド・クインシーは「衝撃」を受け、アヘンの場合と同じように、イギリスの読者に向けて、その反応をすぐに記述すると述べました。どういうわけか、彼の計画は実現しませんでした。しかし、彼は次のように述べています。
ミッドロジアンのある農夫が8ヶ月前にこの薬を服用したという話を聞きました。それ以来、彼は度を越した笑いの発作で近隣住民を困らせており、1月に彼を迷惑者として保安官に告発することにしました。しかし、どういうわけかその計画は頓挫し、8ヶ月後の今、その農夫は以前よりもずっと有頂天になって笑い、最高に幸せな気分で過ごし、とても親切な人となり、近隣住民を大いに困惑させていると聞いています。[21]
1848年、当時広く読まれていた文芸誌『チェンバーズ・エディンバラ・ジャーナル』に匿名の記事が掲載され、著者は読者に対し、ある脅威がフランスを襲っていると警告した。著者によれば、ハシシへの耽溺は医師や医学生から、国の「詩人、理想主義者、そしてあらゆる新奇なものを愛する人々」にまで広がっているという。この薬物の作用、つまり「知覚力、想像力、そして理性」に生じる「変化」について記述した後、著者は、ハシシによる感覚の蠢動を思い描いていたかもしれないイギリス人たちへの重大な警告で締めくくっている。「自然の法則は、いかなるものも罰せられることなく侵害されることはない、そして人間を卓越したものにしている理性も、罰せられることなく誤用されることはない、と断言できるだろう。」[22]
この厳しい警告は、大衆紙や医学雑誌がハシシの効能に関する記事をますます多く掲載するようになって以来、無視されてきたようだ。1850年、国会議員デイヴィッド・アーカートは『ヘラクレスの柱』と題する2巻本を出版し、ハシシに関する自身の経験をこのテーマに関する文献に加えた。[23] 政府関係者がこのような薬物を使用したことで、多くの読者はハシシの危険性は誇張されていた可能性が高いと確信したが、こうした書籍の影響で実際に試してみようと決心した人の数は決して多くはなかった。ハシシ愛用者を増やしていったのは、書籍ではなく、他の使用者との個人的な接触だった。
1858年にリトルズ・リビング・エイジ・マガジンに匿名で寄稿した記事の著者は、読者を慰め、
イギリス人はアヘンやハシシの放蕩の国になる危険はまったくない。そして、その結果が最も破滅的な放蕩の一種に誘惑するほど楽しいものとなった例外的な事例のいくつかをイギリス人に報告することに何らためらいを感じない。[24]
この宣言に続いて、著者は当時の世界におけるハシシやその他の薬物の使用に関する興味深い統計を引用している。「タバコは唯一普遍的な麻薬である。その他の麻薬は、アヘンが4億人、麻が2億から3億人、ビンロウが1億人、コカが1千万人の割合で人類によって消費されている。」[25] 興味深いことに、19世紀半ばのイギリスではアルコール乱用が大きな問題であったにもかかわらず、著者はアルコールについて一切言及していない。
反証となる証拠が山積しているにもかかわらず、イギリスの著述家たちは、同胞のイギリス人がハシシに手を染めているなどという主張を繰り返し否定した。例えば1877年、W・レアード=クロウズは雑誌『ベルグレイヴィア』に「私の知る限り――そして私の調査はかなり広範囲に及んでいるが――これまで後者の薬物(ハシシ)を記録したイギリス人(医師以外)は一人もいない」と記している[26]。レアード=クロウズは、アーカートの『ヘラクレスの柱』や他のイギリスの有名雑誌でハシシについて書かれている内容については知らなかったようだ。しかし、アサシン教団による狂乱的な殺戮の原因がハシシにあるとされていることをある程度は知っていた。ハシシが暴力を誘発するという非難に対して、レアード=クロウズは、自分自身の個人的な経験では、外出して誰かを殺したいという衝動に駆られたことは一度もないと述べている。
おそらく私は暴力的な性格ではないだろうし(彼は結論部分でこう述べている)、殺人を犯す動機も全くない。そしておそらく、人間の生まれ持った嗜好が、ハシシが精神的能力に及ぼす影響をかなり左右するのだろう…思考、言葉、行為のいずれにおいても「不快感の創出」以上に、この薬物の作用と異質なものは、私には想像もつかない。[27]
他のイギリス人も、レアード=クロウの主張に賛同し、イギリス人はハシシ中毒者になる危険性も、大規模な実験を行う危険性もないと主張した。ある作家は「麻薬によって陶酔感や幻覚を見るような状態に陥ることのない気質は、幸いなことに北方の気候では稀である」と述べている。[28] また別の作家は「セラフィム劇場は、人間の経験を陽気なマリオネットのように表現しており、ほぼ避けられない肉体的および道徳的な退廃を代償に、すべての人に開かれている」と記しているが、これはイギリス人の気質とは相容れない状況である。[29]
イギリス人が意識を変容させる薬物の使用を厭わなかったわけではなく、むしろアルコールで満足し、他の精神を変容させる薬物を試す必要性をほとんど感じていなかったのだ。そうした薬物を試したのは、少数派グループのメンバー、芸術家、作家、犯罪者、あるいは学生だった。こうした散発的な事例がマスコミの注目を集め、イギリスの一部でハシシが蔓延しているという印象を与えた。
1886年、古風で落ち着いたケンブリッジ大学の寮で、そのような事件が発生しました。新聞報道によると、学生数名が「ターキッシュ・デライト」を入手したものの、ハシシ入りの菓子に慣れていなかったため、過剰摂取して体調を崩したとのことです。[30] オックスフォード大学にも大麻使用者はいました。[31]
リチャード・バートンも『ハシシを食べる人の物語』の脚注で、「ロンドンで『ハシシの乱交』が起こり、実験者の半数が1週間ソファから出られなくなったという話を聞いたことがある。この薬物は火事場の火夫にとって有用で、男性を熱に鈍感にする奇妙な作用がある。東洋では性交を長引かせる『イムサック』にも使用されており、これについては後述する」と述べている。[32] この観察は1885年に発表されたため、それより以前に起こったと考えられる。
医学雑誌には、この薬物の治療的使用の可能性や過剰摂取した人に起こる副作用に関する記事が溢れかえっていたが、19世紀のイギリスでハシシを扱った唯一の本は、1884年に出版された「イギリスのハシシ摂取者の告白」と題された匿名の著作であり、それは昔のデ・クインシーのベストセラーをモデルにしていた。
「デカダント」
20世紀初頭、19世紀半ばのフランス・ロマン派作家たちを虜にした倦怠感は、イギリス海峡を渡り、アーサー・シモンズ、ウィリアム・バトラー・イェイツ、アーネスト・ドーソン、オスカー・ワイルド、ハヴロック・エリスといったイギリスの作家たちにも浸透した。イェイツは彼らを「悲劇の世代」と呼んだ。
フランスの先人たちと同様に、この新世代の創作者たちは、新たな感覚、ビジョン、そして創作のテーマとなるアイデアを求め、道徳改革ではなく「芸術は芸術そのもののためにあるべきだ」というゴーティエの考えに同意した。作品の中で道徳を忌避したため、彼らは「退廃主義者」と呼ばれた。フランスの先人たちが麻薬にインスピレーションと退屈からの逃避を求めたように、「退廃主義者」たちもまたそうであった。オスカー・ワイルドをはじめとする多くの作家はアブサンを好んでおり、ハヴロック・エリスやW・B・イェイツはメスカリンの嗜好品を好んだ。ただし、イェイツはハシシを嫌ってはいなかった。[33] ダウソンは若い頃はハシシを好んでいたが[34]、アルコールのためにそれを断った。彼らのフランスの同類であるアルチュール・ランボーとポール・ヴェルラーヌは「アブサンとハシシの両方で酔っぱらって、地獄と天国の音楽の詩を書いた」[35]。その中で最もよく知られているのはランボーの『イルミナシオン』で、その印象的な詩句は「これは暗殺者の時代だ…それは子供たちの笑い声で始まり、それで終わる」である。
しかし、ランボーや彼の同時代人の多くにとって、ハシシは目的を達成するための手段であり、それ自体が目的ではなかった。「詩人は」と彼は記している。「長く、計り知れないほど理性的に、あらゆる感覚を混乱させることで、自らを旅人へと変える。あらゆる形の愛、苦しみ、狂気。彼は自分自身を見つけようとし、あらゆる毒を自分の中に使い果たし、その真髄だけを残すのだ。」[36]
「退廃者」たちは、ゴーティエ、ボードレール、ネルヴァル、そしてハシシ・クラブの他のメンバーと同じくらいハシシやその他の薬物を使用していたが、薬物を正式な社交の一部とはしていなかった。また、ゴーティエやボードレールのように、彼らの薬物依存の行動を記録したり、利用したりするような人物もいなかった。さらに、彼らの薬物使用は、特に異常なことではなかったようだ。
西洋医学における大麻
比較的大規模なハシシ実験を開始したのはフランスが初めてでしたが、西洋医学への大麻の導入は、今では無名のアイルランド人医師、ウィリアム・ブルック・オショーネシー博士によるものとされています。今日では大麻に関する先駆的な実験で知られていますが、生前はコレラ治療における点滴による水分・電解質補給療法の導入で最もよく知られていました。しかし、彼の主要な功績は医学とは全く関係がありませんでした。医学の道を離れ、工学に転向したオショーネシーは、インドへの電信システムの導入に尽力し、その功績により1856年にヴィクトリア女王からナイトの称号を授与されました。オショーネシーは1861年、52歳で退役し、イギリスに戻りました。そこで、何らかの理由で名前をウィリアム・オショーネシー・ブルックに改めました。彼はその後28年間生きましたが、医学研究に戻ることはなく、引退後は他の活動に従事していました。
オショーネシーは1833年、イギリス東インド会社に雇われた30歳の外科医として初めてインドを訪れました。彼はカルカッタ医科大学の化学教授も務めていました。インドに到着してすぐに大麻の治療効果に興味を持ったようで、1843年にこの薬に関する研究の概要を報告しました[37]。この報告はイギリスの医学仲間たちの関心を強く惹きつけ、間もなく彼らは自らの医療活動のために大麻を供給するよう彼に強く求めるようになりました。
オショーネシーは論文の冒頭で、大麻の酩酊作用と薬効は東洋諸国では広く知られていたものの、西洋ではほとんど知られていなかったと指摘した。インドとアラブ諸国における大麻使用の簡単な歴史に続いて、オショーネシーは自身が動物実験を行った経緯を述べ、その後言及されることも、さらなる研究が行われることもなかったある観察結果について言及した。オショーネシーの言葉によれば、彼が行った実験は「一つの驚くべき結果をもたらした。肉食動物、魚、犬、猫、豚、ハゲタカ、カラス、そして副官たちは、常に速やかに大麻の酩酊作用を示したのに対し、馬、鹿、猿、ヤギ、羊、牛といったイネ科動物は、投与量に関わらず、わずかな影響しか受けなかったということだ」。この記述から判断すると、オショーネシーは動物に関する予備研究において、まさに徹底的であったと言えるだろう。
オショーネシーは、大麻が動物実験で健康被害を及ぼさないことを確信し、リウマチに悩む患者を対象にその治療効果を検証しました。大麻による治療後、多くの患者が痛みの緩和と「食欲の顕著な増加」、「精神的な快活さ」、そして性的快感を報告しました。
患者を陶酔させる能力に気づいたオショーネシーは、次に、ある患者の狂犬病に伴うひどい症状を緩和しようと試みました。患者は間もなく亡くなりましたが、この薬が患者の苦痛をいくらか和らげ、ジュースや湿らせた米を飲み込むことができるようになったことに、オショーネシーは興味をそそられました。オショーネシーは、コレラ、破傷風、てんかんの治療にも大麻の実験を行い、すべての症例でこれらの疾患の症状が緩和されたと報告しています。
1842年にオショーネシーがイギリスに戻った際、彼は大量の大麻を持ち帰り、薬剤師ピーター・スクワイアに医療用に適した形への変換を依頼しました。この製剤はスクワイア抽出物として知られるようになり、スクワイアとその息子たちはイギリスにおける大麻抽出物の主要かつ最も信頼できる供給業者として名を馳せるようになりました。[38]
スクワイアのエキスが市販されて間もなく、医師たちはほぼあらゆる身体的困難にそれを処方し始めました。それが最初に処方された症状の一つは出産でした。産科における大麻の使用の先駆者であるジョン・グリガー博士は、この薬が全ての女性の陣痛を増強したり、出産の痛みを軽減したりする効果があるわけではないものの、「通常必要な時間の半分以下で分娩を幸せな結末に導くことができ、患者の長期にわたる苦痛と医師の時間を節約することができる」と記しています。[39]
この薬がよく処方される他の症状としては、食欲不振、不眠、片頭痛、痛み、不随意のけいれん、過度の咳、モルヒネやアルコール中毒に伴う禁断症状の治療などがある。
月経過多(過度の月経出血)もまた、大麻が広く投与され、しばしば良好な結果をもたらしてきた症状の一つです。英国の産科医ジョン・ブラウン博士は、「これほど優れた効果をもたらした薬は他にありません…失敗例は非常に少ないので、月経過多の特効薬と呼んでも差し支えありません」と述べています。[40] 同僚のロバート・バソ博士も同意見です。バソ博士の経験では、大麻は「この症状に対する卓越した治療薬であり…月経過多を抑制する力は極めて確実であるため、早期流産の有無が不明な症例の診断に貴重な助けとなります…」[41]。
患者に大麻を投与した最も著名なイギリス人医師の一人に、陰気な老女王ヴィクトリアの侍医であったJRレイノルズ博士がいます。[42] 残念ながら、女王が大麻の他の治療効果の治療を受けていたときに、この薬物の陶酔感を経験したかどうかは誰も知りません。
多くの医師が大麻の薬効について語り尽くす一方で、その作用のばらつきを理由に使用をためらう医師も少なくありませんでした。この問題を克服するため、全国の化学者たちは大麻の有効成分を特定・抽出し、純度と効力を標準化しようと試みました。
1890年代、ケンブリッジ大学の化学者グループ、ウッド、スパイビー、イースターフィールドは、比較的純粋な大麻抽出物を得ることに成功し、これを「カンナビノール」と名付けました。しかし、この発見は災難を伴いました。プロジェクトに取り組んでいる間、イースターフィールドとスパイビーはそれぞれ化学爆発で粉々に吹き飛ばされました。グループの3人目のメンバーであるウッドも同様の状況で瀕死の状態に陥りました。彼は実験室で作業中にカンナビノールを摂取し、意識を失いました。しばらくして、彼が扱っていた化学物質に引火し、実験室は炎に包まれました。幸運にも、煙の臭いに気づいた誰かが駆けつけ、彼を助け、燃え盛る炎から救い出しました。[43]
Reference : The Hashish Club
https://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/history/first12000/8.htm