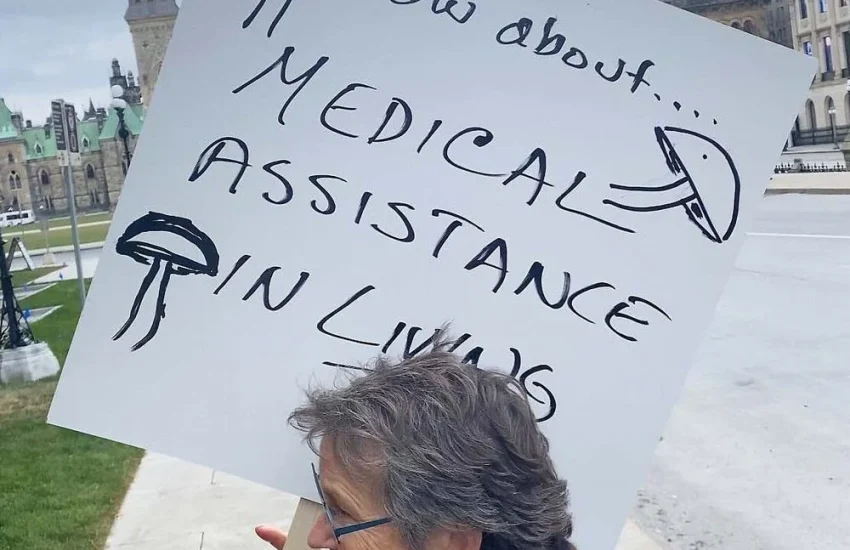初期の結果ではシロシビンによる寿命延長が示唆されているが、この科学は人間の老化に情報を提供できる準備ができているのだろうか?
「マジックマッシュルーム」は、先住民コミュニティで儀式の場で長らく使用され、1960年代のサイケデリック全盛期に広く普及しましたが、その精神活性成分であるシロシビンの臨床応用の可能性が主な理由で、再び主流になりつつあります。これまで科学的な関心は、不安やうつ病などの精神疾患の治療におけるシロシビンの使用に主に集まっていましたが、最近の研究では、老化関連プロセスにおけるシロシビンの役割を示唆する知見が注目を集めました。具体的には、著者である加藤らは、ヒト細胞と老化マウスから得られたデータを提示し、シロシビンが寿命を延ばす薬として作用する可能性を示唆しています。1
老化にシロシビンが効くのはなぜですか?
幻覚キノコが寿命を延ばすという考えは、現代のヒッピーたちのSF的な空想のように思えるかもしれませんが、ある程度の科学的根拠がないわけではありません。体内で生理活性分子であるシロシンに変換されるシロシビンは、セロトニン受容体(特に5-HT 2 A受容体)に結合し、気分、知覚、自己意識の変化をもたらすことで、うつ病や不安症の治療に有望な結果を示しています。2うつ病や不安症は、それ自体がいくつかの老化プロセスを加速させると考えられているため、シロシビンは心理的ストレスを軽減することで老化を遅らせる可能性があるという理論が生まれました。
精神的ストレスによって悪化すると考えられている老化プロセスの一つに、テロメアの減少があります。AMA #76(明日公開予定)でより深く議論するように、テロメアは染色体の末端にあるDNA保護キャップであり、細胞分裂のたびに短くなります。最終的に、テロメアの短縮は細胞を老化へと導きます。老化の典型的な特徴である老化において、細胞は生きたまま成長・分裂を停止し(「ゾンビ細胞」と呼ばれることもあります)、このような細胞の蓄積は炎症を促進する可能性があります。精神的ストレスはテロメアの減少を加速させる可能性があるため、「シロシビン-テロメア仮説」では、シロシビンが精神的ストレスを軽減することでテロメアを維持し、老化を遅らせる可能性があると提唱されています。
しかし、シロシンによって活性化されるセロトニン受容体は脳内だけでなく、免疫細胞や腸など体全体に分布しています。このことから、シロシビンは心理的効果を通じて老化に影響を与えるだけでなく、全身に直接的な影響を及ぼす可能性も示唆されます。活性酸素種(ROS)の産生が体内のROS中和能力を上回る状態である酸化ストレスも組織損傷を促進し、老化の特徴的な症状です。シロシンは5-HT 2A受容体を活性化することでROSの放出を抑制できる可能性が示唆されています。3酸化ストレスはテロメアの消耗を加速させ、慢性炎症を引き起こす可能性もあるため、シロシビンによるROS抑制は複数のメカニズムを通じて老化に影響を与える可能性があります。
まとめると、シロシビンが老化を遅らせるとされる様々な経路が考えられており、主に心理的ストレスと酸化ストレスの両方を軽減することでテロメアの消耗を遅らせるという仮説に基づいています。しかし、この仮説は相関関係の連鎖と理論的なメカニズムの関連性に頼る脆弱な仮説でもあります。それぞれの関連性は実験的な検証と因果関係の説明を必要とする大胆な推測であり、加藤らはより深い調査を行うよう促しています。
研究について
シロシビン-テロメア仮説を検証するために、著者らは主に研究室で培養されたヒト細胞(肺線維芽細胞)を用いた実験に頼り、さらに生きた老齢マウスでの概念実証実験を補完した。
細胞培養実験では、ヒト細胞をシロシンまたは対照群(ビヒクル)で処理し、細胞が老化状態に達するまで分裂を継続させました。老化状態に達するまでの細胞分裂回数は、細胞の複製「寿命」とみなすことができます。対照細胞と比較して、10μMの濃度のシロシンで処理した細胞は細胞寿命が29%延長し、さらに10倍の用量で処理した細胞では、対照群と比較して57%の延長という、より大きな効果が観察されました。これらの知見は、処理細胞における細胞周期停止(細胞の成長と分裂を遅らせたり停止させたりすること)の細胞マーカーの減少と、増殖マーカーの増加によってさらに裏付けられました。これらの結果を総合すると、シロシンをヒト細胞に直接投与すると、細胞老化が遅れることを示しています。
シロシンを投与した細胞は、ROS産生量が減少し、テロメアが長くなった。幅広い濃度範囲(0.01~100 μM)において、シロシンは対照群と比較して、老化細胞(培養60~63日)のROS産生量を用量依存的に減少させ、最高用量では若年細胞(培養0~4日)のROSレベルと同等かそれ以下のROSレベルに達した。同様に、対照細胞は老化に伴いテロメア長が短縮したのに対し、シロシンを投与した細胞はテロメア長を維持した。これらの細胞は培養細胞であり、心理的ストレスの影響を受けていないことから、シロシンはROS産生量の減少によるものなのか、あるいは別の未知のメカニズムによるものなのかは不明であるが、末梢細胞への直接的な作用を通じてテロメア長に影響を与える可能性があると結論付けることができる。
しかし、この研究が注目を集めるきっかけとなったのは、30匹のメスのマウスを用いた概念実証的な生存実験でした。著者らは、これらのマウスに19ヶ月齢(人間の60~65歳にほぼ相当)から、月に1回、シロシビンまたは溶媒を経口投与しました。10ヶ月の投与後、シロシビン群の約80%が生存していたのに対し、対照群ではわずか50%でした。シロシビン投与群のマウスは、毛色がより濃く、より豊かで、まだら状の灰色の部分が減り、より健康的に見えました。
このように、ヒト細胞において、シロシンは細胞老化を複数の関連する特徴(老化の抑制、酸化ストレスの低下、テロメアの維持)において遅らせることが示唆されました。生きた動物において、シロシビンは高齢動物の生存率を高め、老化の視覚的兆候を改善しました。
欠陥のある前提
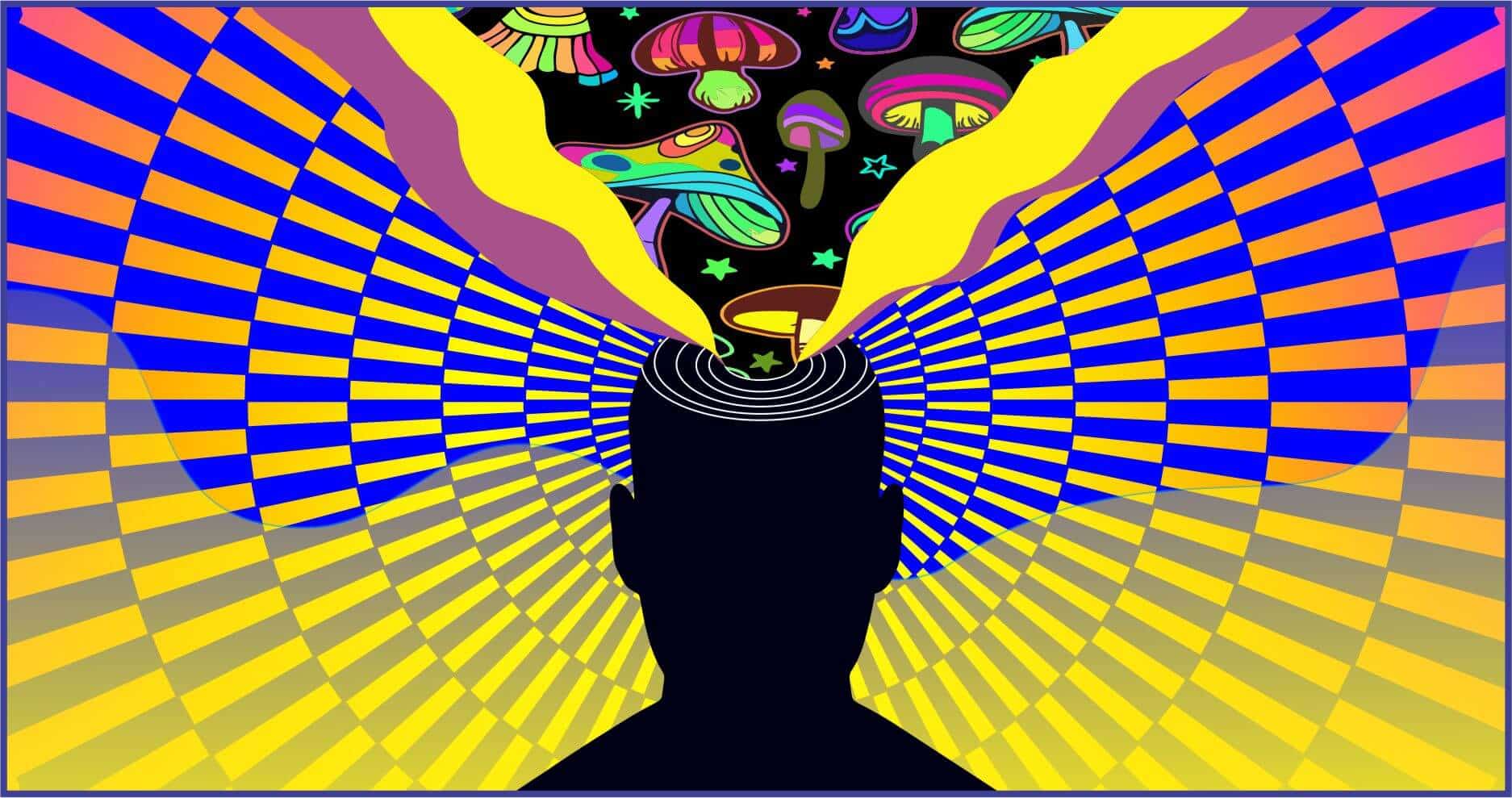
表面的には、加藤らの研究結果は印象的であるように見えるが、残念ながら、それは欠陥のあるメカニズムの根拠という不安定な基盤の上に成り立っている。テロメアは細胞分裂を繰り返すことで短くなるのは事実だが(これはテロメアを再構築する酵素によって部分的に相殺される)、テロメアの長さで寿命を確実に予測できる、あるいはテロメアの消耗を遅らせると寿命が延びるという証拠はほとんどない。種を超えて、テロメアの長さと寿命の間には一貫した関係がない。例えば、マウスはヒトよりもはるかに長いテロメアを持っているが、寿命はわずか数年だ。暦年齢との相関関係さえも弱い。2021年に98種のテロメア長について行われたメタ分析では、年齢との非常に緩やかな逆相関関係が認められたのみで、しかも成体においてのみ認められた。4幼体では全く相関がなく、分析では成体と幼体の間のテロメア長の明確な違いさえ見つからなかった。言い換えれば、テロメアの長さは細胞が何回分裂したかを反映しているかもしれませんが、老化の信頼できる指標ではありません。
見かけの寿命への影響をどう考えればよいでしょうか?
テロメアの長さを維持すれば寿命が延びるという根拠は薄いものの、この研究データは、プラセボではなくシロシビンを投与した場合、実験終了まで生存する動物の数が増えたことを確かに示しており、これは無視できない観察結果です。テロメアとは関係なく、シロシビンが同様の効果を発揮する経路は他にも確かに数多く存在します。しかしながら、この実験は寿命延長試験に通常期待される厳密さと完全性において、ある程度の基準を満たしていなかったことは指摘しておく価値があります。
第一に、研究者らは強制的なエンドポイントを設定した。対照群の動物の50%が死亡した時点で、研究は中止された。つまり、シロシビン投与群の真の中央寿命(これらの動物の50%が何歳で死亡したか)も、投与によって最大寿命が延びたかどうか(最長寿の動物がどれだけ生き延びたか)も分からない。これらの数値がなければ、シロシビンが真の寿命延長薬であるという主張は、せいぜい時期尚早と言える。この研究が本当に示しているのは、シロシビンが老化の限界を押し上げたということではなく、研究条件下で投与期間中に死亡したマウスの数が減ったということだ。これは、老化を遅らせると主張する介入について議論する際に重要な違いである。
しかし、シロシビンが本当にこれらのマウスの寿命を延ばしたと仮定しましょう。しかし、これらの結果を人間に適用するには、まだ乗り越えなければならないハードルがあります。最も明白なのは投与量です。動物には、ほとんどの人間が許容できる量をはるかに超える、かなり大量のシロシビンが投与されました。15 mg/kg という用量は、(代謝の違いを考慮した標準的な相対成長法を用いて)人間に換算すると約 1.2 mg/kg、体重 60 kg の人間であれば約 72 mg になります。ちなみに、現在のシロシビンの治療試験では通常約 25 mg が使用されており、サイケデリックコミュニティでは 50 mg が「ヒーロー用量」とされています。言い換えれば、マウスのレジメンは、ヒーロー用量を毎月 1 回、何年も続けて服用することになります。
なぜ彼らは動物にこれほど高用量を投与したのだろうか?研究者たちはまず、相対成長尺度を用いて代謝の違いを補正し、次にマウスとヒトにおける薬物の半減期を比較した上で2つ目の補正を加えた。つまり、マウスの薬物代謝が速いという同じ要因を2度補正したことになる。このアプローチは、効果発現の可能性を最大化することを目的とする原理実証試験においては妥当性があるかもしれないが、ここで用いられた投与計画がヒトへの使用に関する現実的なシナリオに当てはまらない可能性が高いため、応用可能性については明白な疑問が生じる。
証拠ではないが、何もないわけではない
方法論的な限界と不安定な根拠にもかかわらず、この研究は探索的研究として重要な目的を果たし、さらなる調査のための興味深い疑問を提起しています。
まず、真のメカニズムとは一体何なのでしょうか?シロシビンは5-HT 2A受容体に作用することでストレス反応を変化させ、全身性炎症と酸化ストレスを軽減する可能性があります。これはテロメア短縮の抑制よりも重要なメカニズムなのでしょうか?あるいは、マウスにおける寿命延長効果は、活性酸素種(ROS)に対する見かけ上の細胞自律的効果ではなく、ストレス緩和による心理的効果に関係しているのかもしれません。そして、これは重要な疑問を生じさせます。生理学的効果が現れるためには、心理的効果を経験しなければならないのでしょうか?幻覚作用のない類似物質は、サイケデリックなトリップなしに、同様の下流変化を引き起こすことができるのでしょうか?
第二に、シロシビンはラパマイシンのような「ゴールドスタンダード」の老化防止剤と比べてどうなのでしょうか?ラパマイシンは、性別、品種、研究室を問わず、中央値と最大値の両方で寿命を延ばし、その過程で明らかな機能的利点を示してきました。対照的に、シロシビンについては、強制エンドポイントを用いた、単一の性別を対象とした小規模で再現性のない研究が1件あります。現時点ではシロシビンとラパマイシンは同等ではありませんが、将来の実験によって同等のレベルに達する可能性はあるでしょうか?シロシビンが介入試験プログラム(ITP)の厳格な試験を受けるようになれば、その寿命延長効果に、より信頼を置く理由が生まれるかもしれません。
最後に、機能的アウトカムはどうでしょうか?生存曲線や毛色は、老化生物学のほんの一部に過ぎません。シロシビンは、高齢動物の除脂肪体重を維持し、虚弱性を軽減するのに役立つのでしょうか?認知機能の向上や免疫能の維持についてはどうでしょうか?こうした指標がなければ、マウスが単に長生きしただけなのか、それとも実際にはより良い生活を送っていたのか、推測するしかありません。
結論

シロシビンに関する研究は必然的に議論を巻き起こします。おそらく、シロシビンがスケジュールI物質(「乱用される可能性が高い」かつ「医療用途が認められていない」と分類されているが、どちらの分類も深刻な疑問を呈している)に指定されているためでしょう。そのため、研究結果を全面的に否定する人もいれば、精神活性薬の新たな時代の到来を告げるものとして歓迎する人もいます。しかし、現実は、いつものことながら、より微妙なものです。
この研究は、そのシグナルがすべて「正しい」方向を指し示している点で興味深い。すなわち、試験管内における細胞の寿命延長、酸化ストレスの軽減、テロメアの維持(それが何を意味するかは別として)、そして高齢マウスの生存率向上である。しかし、正しい方向を指し示していることと、それが証明されたわけではない。マウス実験は寿命を厳密に検証するように設計されておらず、テロメアに関する根拠は不明確であり、投与戦略は明らかにトランスレーショナルな課題を生じさせている。
それでも、これは価値のある研究の糸口となる。もしシロシビンの効果が本当にストレス緩和とセロトニン作動性シグナル伝達によって引き起こされるのであれば、メンタルヘルスと老化に関する私たちの考え方に重要な一面を加えることになるかもしれない。今問題となっているのは、これらの初期の示唆に富む発見が、より慎重な実験の重みに耐えられるかどうかだ。それまでは、シロシビンは治療効果が期待される刺激的な分子であり続けるものの、長寿分野ではまだ実証された存在ではない。
参考文献
1. Kato K, Kleinhenz JM, Shin YJ, Coarfa C, Zarrabi AJ, Hecker L. シロシビン投与は細胞寿命を延長し、高齢マウスの生存率を向上させる。NPJ Aging. 2025;11(1):55. doi:10.1038/s41514-025-00244-x
2. Remot F, Ronget V, Froy H, et al. 加齢に伴うテロメア長の減少:非ヒト脊椎動物におけるメタアナリシス. Mol Ecol. 2022;31(23):5917-5932. doi:10.1111/mec.16145
3. Goldberg SB, Pace BT, Nicholas CR, Raison CL, Hutson PR. シロシビンの不安および抑うつ症状に対する実験的効果:メタアナリシス. Psychiatry Res. 2020;284(112749):112749. doi:10.1016/j.psychres.2020.112749
4. Wiens KR, Brooks NAH, Riar I, Greuel BK, Lindhout IA, Klegeris A. シロシビンの精神活性代謝物であるシロシンは、5-HT2受容体依存的にミクログリア細胞の特定の神経免疫機能を調節する。Molecules. 2024;29(21):5084. doi:10.3390/molecules29215084
Reference : A critical look at the lifespan-extending promise of psilocybin
https://peterattiamd.com/psilocybin-and-lifespan